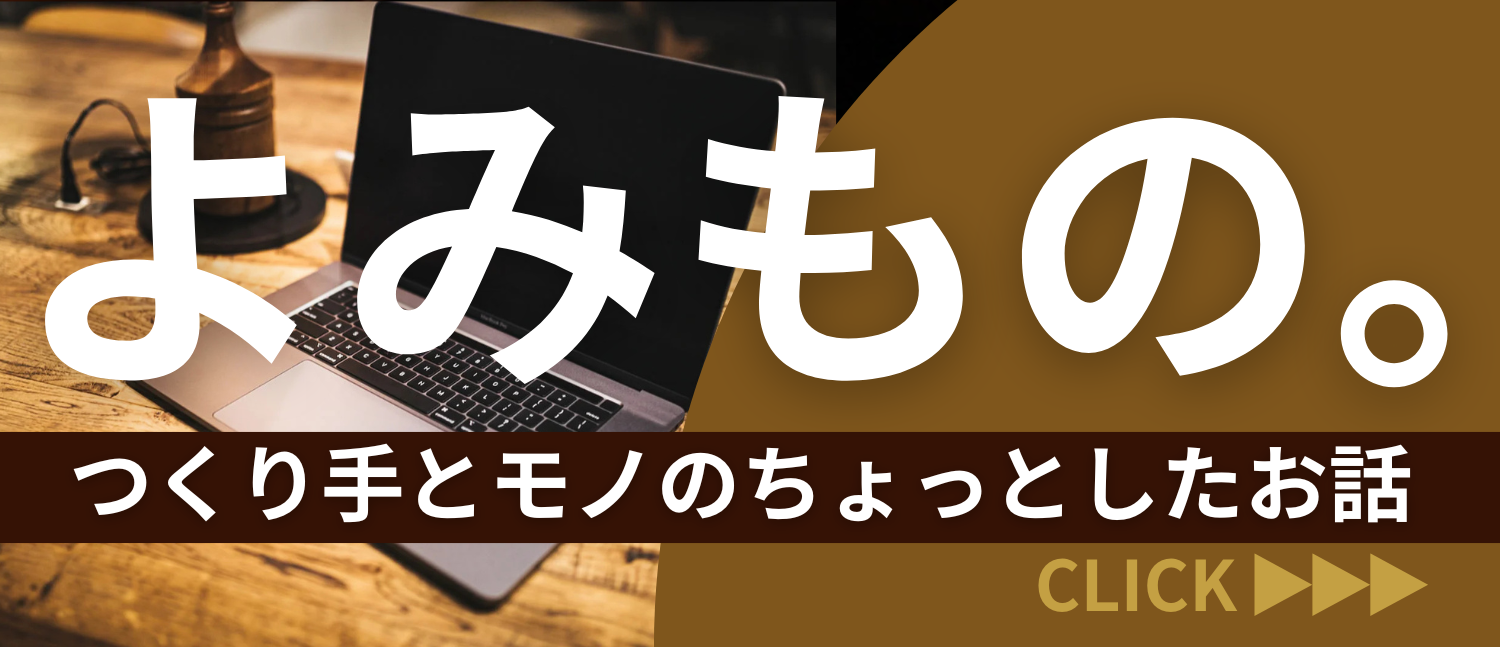北陸の冬の郷土料理「かぶらずし」

かぶらずしは北陸の郷土料理
1.冬季の保存食
かぶらずしは日本の伝統的な発酵食品の一種です。
まだ「お酢」が高価で貴族しか手に入れることができなかった時に作られていたと想像されます。その昔、醤油がなかった時代にはお酢が醤油の代わりに使われていたようです。つまりお刺身に当たるものはお酢を付けて食したのです。
◆富山と石川の郷土料理
米麹を使った発酵食品のなれずしは、富山、石川を中心とした寒い期間が続く北陸地方で、冬に好まれる郷土料理として伝わってきました。タンパク源として主にブリなどの魚と、野菜のカブを使います。カブは北陸や関西ではカブラと言います。カブは昔の野菜の中では栽培効率がよい野菜でした。
「三国志」の時代、諸葛亮孔明は戦地に着くとカブの種を蒔き、60日後には兵士の食糧にしたと言います。そのためカブは「諸葛亮」の名が付いたこともあるようです。
かぶらずしは魚、カブのほかに塩、米麹、米、人参、柚子なども加えられることが多いです。
昔の作り方を想像すると
1. 魚がたくさん獲れた時に塩漬けして保存する
2. カブが大きくなったら塩漬けする
3. カブに魚を挟み、糀甘酒で漬け込み、発酵させ熟成させる
4. 塩度により、数日から数週間発酵させた後に食べる
魚のうま味と塩気、シャキシャキとしたカブの口触り、さらに米麹の自然な甘みが合わさった絶妙な味わいが特徴で、発酵による独特の風味が好評です。
そのまま食べるのが一般的で、ご飯と一緒に食べたり、お酒のおつまみにももってこいです。冬季の保存食にもなり、正月料理としても楽しまれています。
◆なぜ北陸の特産なの?
北陸は雪に閉ざされることが多く、越冬するための食糧が必要でした。ブリなどの魚も獲れる時には大漁ですが、毎日安定して獲れるものでもありません。発酵させれば、おいしい上に保存もでき、一石二鳥となります。発酵は温度管理がとても大変なので、低温が続く北陸の気候に合っていたのでしょう。
江戸時代、100万石の所領を得ていた加賀藩下。高い文化性をはぐくんだ北陸で、ふんだんなお米と高級な鰤を使うことができたことも、とても贅沢な特産品をはぐくんだ背景と言えます。

◆かぶらずしに使う魚
ブリ(鰤)が最も親しまれています。脂が乗ってうま味が強く、発酵させるとおいしさが増します。特に冬の富山湾で水揚げされるブリは「寒ブリ」として有名で、脂肪分が多く最高の品質です。
サケもよく使われます。癖がなく、他の素材との調和が取れやすいのが特徴です。
魚を選ぶには新鮮さが重要です。特に塩漬けして発酵させるため、元々の品質が味に大きく影響します。脂が程よく乗っている魚を選ぶと、発酵後の味わいが豊かになります。特にブリは冬季の脂乗りが良いものが適しています。骨をしっかりと取り除いておくことで、食べやすさが向上し、子どもや高齢者が食べる場合にも安心です。
◆かぶらずしとサバ
かぶらずしには通常、サバ(鯖)はあまり使われません。サバは非常に風味が強いので、家庭でかぶらずしをつくるときは、サバはとても作りやすくおいしく仕上げることもできます。このため、昔から慣れ親しんだ方に強い支持もあるのです。長く作ってきた家では、おばあちゃんの味、お母さんの味として懐かしむ人も多いのです。
◆家庭の味
かぶらずしは、現代でも一部の家庭で作られていますが、その作業の手間と時間から、昔ほど一般的ではなくなってきています。同時に、市販品が広く手に入るようになったため、家庭で作る頻度は減少してきました。家庭料理として伝わってきた理由は、地域の伝統や家族の習慣として、世代を超えて作り続けられてきたからです。正月には欠かせないという家庭もあります。また家庭ごとに独自の味付けがあるのも理由の一つでしょう。自分で作ることで、使用する材料や塩分量を調整できるため、健康に気を使う家庭では手作りが好まれることもあります。
家庭でかぶらずしを作る際には、以下の点に注意が必要です。まずは温度管理ができる環境が必要です。糀甘酒を作る時は、温かい温度を一定に保つ必要がありますし、熟成する時は10度以下を保つ必要があります。衛生管理面では、発酵食品であるため発酵条件を整える必要があります。塩漬けと発酵に手間と時間がかかるため、計画的に作業を進める必要があります。材料の選び方も大切。良質な魚やカブ、そして新鮮な米麹を選ぶことで、味の質が向上します。
近年では、専門店で高品質なかぶらずしが購入できるようになり、手作りの代わりにこれらを利用する人が増えています。忙しい現代人でも、伝統の味を楽しむことができるのです。
◆かぶらずしの選び方
以下の点に注意して選ぶと、良質なかぶらずしを選ぶことができます。
1.カブの状態
カブは鮮やかな白色で、身が締まり、堅さのあるものがふっくらとカリッと仕上がっています。
2.魚の品質
魚の色が鮮やかで、脂ののっているもの。
3. 発酵状態
糀で付けていくと水分が出てきて水に浸かった状態になります。この水分の甘酸っぱい状態がおいしいサインになります。水分に薄く白い膜の張ったものは、酸味が強いことがあります。
4. 味
塩味が強すぎず、かつうま味が十分に感じられるものがよいです。塩分のバランスが取れているかを確かめたいものです。米麹の自然な甘みと発酵によるほのかな酸味があり、歯応えがあるものがおいしいです。
◆賞味期限
かぶらずしの賞味期限は、保存方法や作り方、特に発酵の状態によって異なります。
食べごろも好みによって差があります。甘いかぶらずしが好きな方は早めに、乳酸発酵の甘酸っぱい味がお好みの方は、少し熟成させて好みに合わせて召し上がるのがおすすめです。
保存方法は、漬け込み桶から出してある場合、できる範囲で空気にあてないことがコツになります。麹菌などは空気が好きなので空気にあたると発酵がとても進みます。冷蔵庫で保管し、お召し上がりの時は、冷蔵庫内で20分ほど空気にあてて食べるのがよいでしょう。
◆子どもでも食べられますか?
かぶらずしは発酵食品ですが、子どもでも食べられます。発酵食品特有の酸味や香りがあり、これが子どもにとってなじみがない場合があります。初めて食べる子どもには少量から試してみるとよいでしょう。その反応を見てから量を調整します。ご飯と一緒に食べることで、風味が和らぎ食べやすくなります。子どもには魚に対するアレルギーのある場合もあるので、アレルギー反応には注意しましょう。
かぶらずしは日本の伝統的な料理であり、子どもに風土や食文化を教える良い機会にもなります。一緒に作ってみるのも楽しい体験となるでしょう。
2.かぶらずしは栄養豊富な食べもの
◆麹(こうじ)の力
麹とは、米、麦、大豆などの穀物に麹菌を繁殖させたもの。味噌や醤油、日本酒など、日本の食文化に欠かせません。
かぶらずしに使うのは米麹です。米麹菌と乳酸菌の働きで米を溶かし、甘みを引き出し、魚のタンパク質、脂質、お米の炭水化物は、カブについた乳酸菌と麹菌の力を借りて400種類以上のうまみと数十兆個の乳酸菌を醸し出します。そのおいしさが一度に口の中に広がることで、豊かな味わいを醸し出し、バランスの取れた栄養が体に染み渡っていきます。
◆健康と美容
一般に発酵食品には、ビタミンB群による代謝アップ、善玉菌による腸内環境の調整、悪玉コレステロールの除去、ビタミンCやミネラル、カロテンなどによる抗酸化作用があります。カブ自体にもビタミンCが含まれ、老化やがん、免疫力の低下をもたらす活性酸素の働きを抑えてくれます。美肌のためにもうれしい食材です。発酵によりビタミンB群やアミノ酸、乳酸菌などが増え、栄養価が高まります。これにより、冬季の栄養補給に役立つ食品となっているのです。
魚のタンパク質とカブや米麹の炭水化物・食物繊維がバランスよく摂取できるため、健康的な食品とされてきました。
カブは低カロリーで低糖質、食物繊維が豊富で腹持ちも良いので、ダイエットにはおすすめの食材。カブの葉には、ビタミン類やミネラルも豊富で、特に美肌効果のあるビタミンCや糖質の代謝をサポートするビタミンB1が豊富に含まれており、ダイエットだけではなく美容にも役立ちます。根の部分には消化酵素のアミラーゼを含んでおり、これはでんぷんの消化酵素としてはたらき、胃もたれや胸やけを解消する働きや整腸効果があります。発酵過程で乳酸や酢酸などの有機酸が生成されるため、酸味が感じられます。この酸味は、食品の味を引き締める役割を果たし、さわやかな風味をもたらします。また発酵過程で生じる揮発性化合物やアミノ酸の分解産物が香りを形成し、食品に深みと複雑さを与えます。

◆カブの品種
かぶは別名で「すずな」とも言われ、春の七草のひとつでもあります。 赤かぶ、白かぶ、大小といろいろありますが、最も一般的なものは白い「小かぶ」。かぶらずしには白い大カブを使います。大カブは引き締まった栽培を行うことにより「梨」や「甘柿」のような上品な甘さになり、歯ごたえもふっくらとした中にカリッとしたものになります。
石川県のかぶらずしに一般に使用される品種は金沢青カブ。金沢周辺でよく使われる品種です。肉質が緻密で堅さがあり、温度変化を受けにくいことが特徴です。
京都の伝統野菜の聖護院カブ(しょうごいんかぶ)は、他の品種に比べて大きく、ジューシーな肉質が特徴で、漬物にも適しています。
こうした中で、『よね田』は寒暖差の大きい、南砺地方で収穫される身が引き締まって甘味を増した「白カブ」を使っています。栽培には労力がかかる昔ながらの品種ですが、この肉質や歯応えを超える新しい品種は出てきていないと言います。
3.日本の発酵食品
◆かぶらずしの歴史
1. 江戸時代以前(17世紀まで)
日本では古来から発酵技術が発展してきており、かぶらずしの原形となる食品も、江戸時代以前から存在していたと考えられています。
2. 江戸時代(17世紀〜19世紀)
江戸時代には、特に北陸地方で発酵食品が盛んに作られ始めました。この時期には保存技術の一環として、魚を使った発酵食品が普及してきていました。
富山県や石川県は、豊富な海産物と農産物が利用できる環境だったため、これらを活かして冬季に備えた保存方法としてかぶらずしが発展しました。
3. 明治時代(19世紀末〜20世紀初頭)
明治時代になると、かぶらずしは商業的にも取り扱われるようになり、地域の特産物としての地位を確立していきます。
地元の庶民にとって、冬の寒い季節の保存食としてだけでなく、正月や特別な行事のごちそうとしても楽しまれるようになりました。
4. 戦後から現代(20世紀〜現在)
戦後、かぶらずしは家庭での手作りから市販品としての普及が進みました。現在では、地域を代表する郷土料理として広く知られるようになっています。
現代においても、地域の風土や食文化を守るため、多くの家庭や料理店でかぶらずしが作られ続けています。観光客にもその魅力が広がり、富山県や石川県を訪れる際の名物の一つとなっています。また宅配便が冷凍配送に対応したことで、贈答品としても爆発的に増加しました。
◆その他の発酵食品
日本各地の伝統的な発酵食品や漬物は、地域ごとに独自の風味や製法を持っており、かぶらずしと同様に古くからの食文化として親しまれています。
・鮒ずし(ふなずし)
琵琶湖の鮒を使った発酵食品。魚の内臓と共に米と塩で漬け込み、長期間発酵させて作ります。独特の強い風味が知られています。
・へしこ
鯖を米糠と塩で漬け込んで作る発酵食品で、福井県のものが有名です。米糠の風味が特徴で、保存性が高いのが特徴です。
・なれずし(馴れ寿司)
魚と米を発酵させた寿司。その風味は地方ごとに異なり、独特の酸味とうま味が特徴。西日本、特に和歌山県や奈良県が知られています。
・漬物
漬物は日本各地でさまざまな種類があります。例えば、奈良漬け・しば漬け(京都府)、広島菜漬け(広島県)、ぬか漬け(関東地方)など、地域特有の野菜や製法を用いたものがそろっています。
・いかの塩辛
イカの内臓を使った塩辛で、発酵による深い味わいがあります。酒のつまみとしても人気。北海道や北陸地方が有名です。